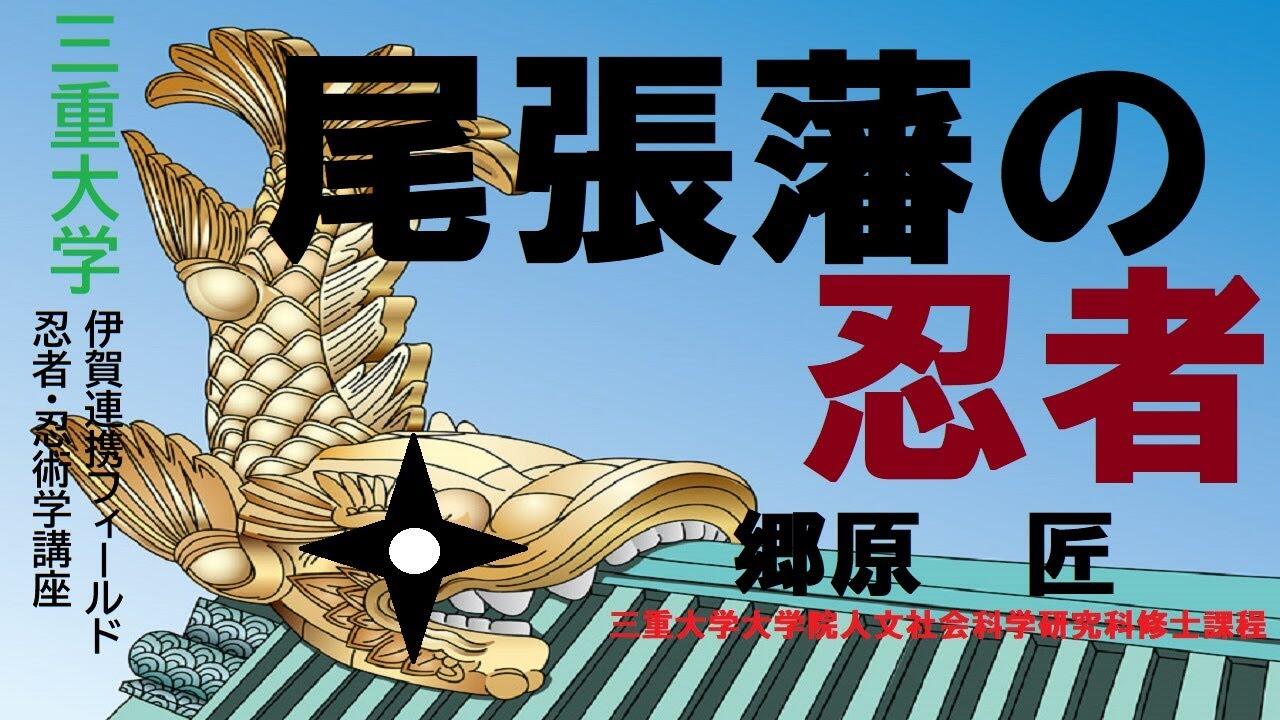研究
第6回「尾張藩の忍者」(前期)
「尾張藩の忍者」要旨
郷原 匠
本発表では、尾張藩に仕えた忍びについて検討を行っている。特に「甲賀五人」と呼ばれた甲賀出身の忍びに焦点を当て、先行研究を踏まえつつ、その出自、設置期間、構成員、支配頭、給禄と格式、担った職務といった制度面・職掌面からの考察を行った。
甲賀五人は延宝7年(1689)に、初代木村奥之助の取り次ぎによって「御鉄砲打」として召し抱えられた。江戸期を通して、毎年甲賀から名古屋へ出仕し、鉄砲稽古と年中行事「矢田河原鳥銃惣放」の職務を担っていたとされる。享保8年(1723)には、大和郡山藩への隠密業務も行っていた。
そして「御土居下忍び」、「和田孫八」、「柘植家」といった尾張藩の他の忍びとの比較も行った。御土居下忍びは門番や名古屋城の警備、和田孫八や柘植家は参勤交代の御供を務めていたことが分かった。これらの職務は江戸期における忍びの一般的な職務であったことが、現在の定説となっている。
したがって鉄砲関係の職務のみに従事していた甲賀五人は、尾張藩において一種の儀礼・象徴的存在であり、あまり忍びらしい活躍は期待されていなかったと思われる。近世忍者史においても特殊な位置付けが可能となるから、今後も甲賀五人に注目していきたい。