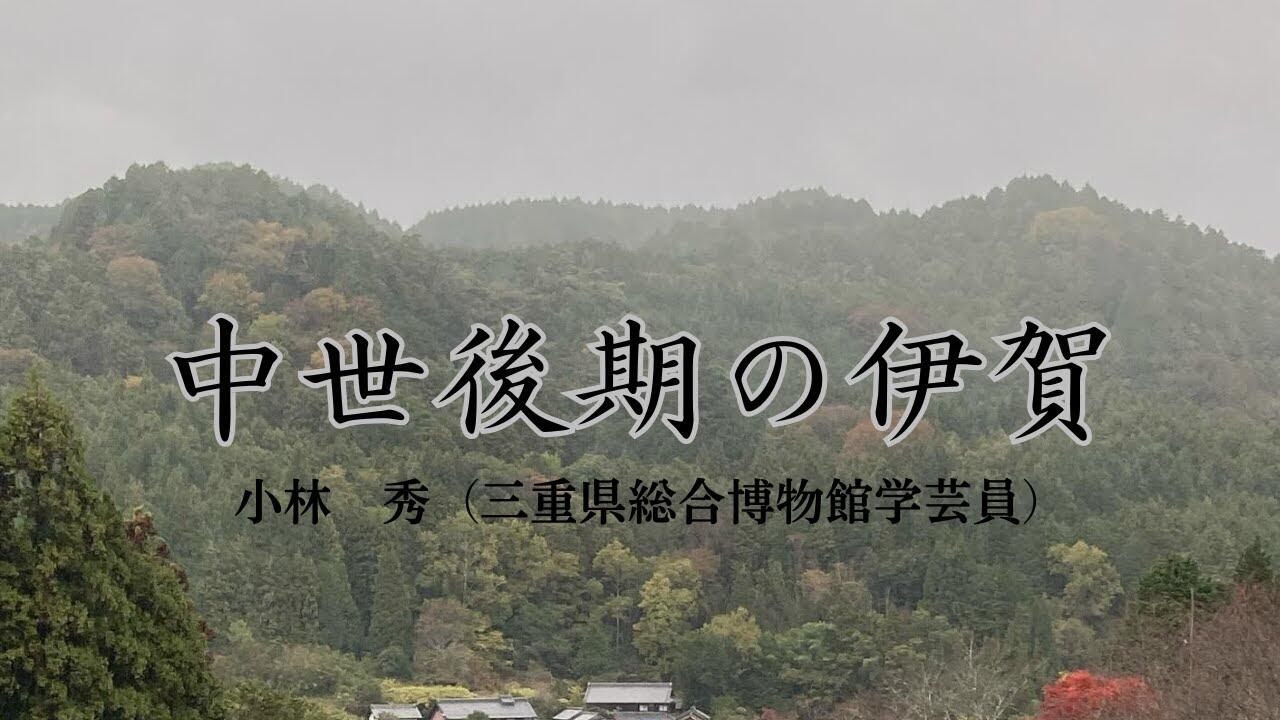研究
第3回「中世後期の伊賀」(前期)
「中世後期の伊賀」要旨
小林 秀
中世後期の伊賀は守護権力が弱く、相対的に国人領主らは自立性の強い存在であった。戦国時代には、彼等「伊賀衆」は、百から三百ほどの単位で「伊勢国司」として知られる北畠氏や紀伊・山城国等の守護であった畠山氏など、主に近隣大名や在地領主等によって軍事動員された。彼等の戦闘力は高く、城塞の守備をはじめ、時にはその主戦力として活動していたことが、残された諸記録から明らかとなる。彼等が他国の大名等と恒常的な扶持関係にあった可能性もあるが、伊賀国だけで約七百もの城・館のひしめいていた状況から、その多くは、その都度人別で報酬の与えられる、「傭兵」的なものであったと推定される。史料中で「伊賀衆」など、個人よりも集団として記述されることの多い彼等は、血族衆を核として集団化し、『満済准后日記』の記事に見える、北村方・福地方・日置方のいわゆる「柘植三方」に代表されるような、地縁的な繋がりによって結合した集団が、伊賀国の各所に形成されていたと考えられる。